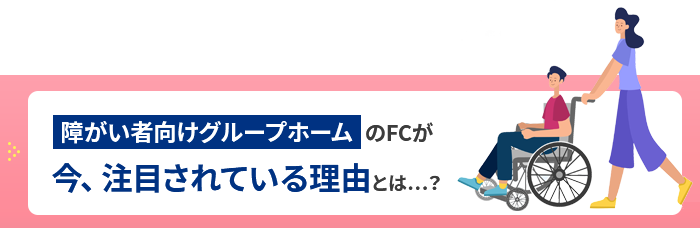共生型グループホーム
グループホームにはたくさんの形態がありますが、ここでは共生型グループホームについて、わかりやすく説明しています。運営する上での目的や、メリット・デメリットを踏まえて理想的な運営方法スタイルを探ってみましょう。
共生型グループホームとは
共生型グループホームは、身体・精神に障害を抱えている人と、高齢者が共存しながら利用する形態のグループホームです。自立した生活を送ることが難しい人がサポートを受け、地域と関わりを持ちながら心を豊かにしながら生活することを目的としています。共生型サービスは、2018年に介護保険制度改定により生まれたサービスです。介護や障がいを抱える人たちが、同じグループホームに住み共存しています。
共生型グループホームの目的とは
共生型グループホームは、以下5つの視点に着目した運営をしています。
- 重症心身障害者・知的障害者等・認知症高齢者が地域と、共生型の暮らしを実現する
- 自宅・通所・施設の他に共生型グループホームの選択肢を増やし、多様な暮らしを実現しその人らしさを大切にする
- 生活できる場所の選択的循環による、社会的リハビリ効果
- 年齢や障がいレベルを超えた交流を実現し、役割を獲得
- 身体障がいや高齢者になっても、住み慣れた場所で暮らし続けられるこだわりを大切に地域ケアの実現
共生型グループホームは、疾病や障がいを抱えている人の地域生活を支えるためにあります。共に支え合い役割や生きがいを持ち、人々や地域と触れ合いながら、自律的な地域の実現を目指しているのです。これまでに抱えていた障がいや生きづらい環境をクリアにし、自分らしく生きていくだけでなく、相手を思いやり育む心も育てられるでしょう。
共生型グループホームのメリット・デメリットとは
共生型グループホームには、メリット・デメリット両方の面が存在します。それぞれのメリット・デメリットを詳しく見てみましょう。
共生型グループホームのメリットとは
人々の活気が生まれて明るい環境が生まれる
共生型グループホームは、たくさんの人々が暮らしている施設です。高齢者と障がい者が一緒に暮らすことで、多彩な交流ができます。世代を問わず暮らせるグループホームならではの交流ができる点は、メリットと言えるでしょう。障がい者のみ、高齢者のみが集まるグループホームとは違った刺激を互いに得られ、脳の活性化も期待できます。
グループホームの利便性が高い
共生型サービスを利用すると、必要なリハビリ施設やサービス事業所に通わなくて良い点はメリットと言えるでしょう。手続きをそれぞれの施設を利用しなくても一括ででき、煩わしさもなく利便性が高いのも魅力的。事業所や場所はもちろん、環境も変わらないため、利用者自身が快適に過ごせるでしょう。
運営コストが効率的で経済的
共生型グループホームは、利用者だけでなく運営者にとってもメリットがあります。土地や建物などの固定資産は、1事業所分で済むため経済的なのです。また運営基準や指定基準の認定は、介護サービスか障がい福祉事業所のいずれかで良い点も魅力的。介護と障がい事業所の両方、指定を受けられるのです。一般的に2つの事業所を運営するよりも、効率的かつ経済的な点がメリットと言えるでしょう。
共生型グループホームのデメリットとは
サービスレベル低下とスタッフの仕事量増加懸念
共生型グループホームは、障がい者と介護者が両方共存して暮らす場所です。それぞれに必要なサポートやケアが異なるため、スタッフの仕事量が増加する点はデメリットと言えるでしょう。共生型グループホームでは、高齢者だけや障がい者だけではなく、年代もさまざまな人たちが共存しています。活動時間帯も異なり、状況把握を一度にしづらいため、視野を広くして注意深くサポートが必要です。提供できるサービスレベルの低下も、懸念されるでしょう。
感染症リスクが高い
さまざまな年代の人々が共存するため、感染症リスクが高まる点もデメリットと言えるでしょう。共生型グループホームは運営形態によって、さまざまな年代の方が利用します。特に、幼老共生型グループホームの場合、子どもからの感染リスクが高いため要注意。高齢者は免疫力や抵抗力が低いため、1人が感染してしまうと、クラスター発生の可能性も懸念されます。感染症対策マニュアルや施策を明確化させ、あらゆるリスクに備えておきましょう。
まとめ
共生型グループホームは、障がい者や高齢者などが共存しながら生活する施設です。それぞれが支え合い、地域の方とコミュニケーションを取りながら毎日の生活を充実させられます。共生型ホームのメリット・デメリットも踏まえて、「どのような運営スタイルが理想的なのか」「利用者と運営者双方が明るく心地よく過ごせるか」などを一度しっかり検討してみましょう。当HPでは、共生型グループホームの運営を目指せるフランチャイズ会社や、それぞれの会社の特徴や強みをわかりやすく解説しています。共生型グループホーム運営に興味がある方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
グループホームフランチャイズ
FC本部の選び方について知る
オススメのグループホーム
フランチャイズ3選
Kensei 共生.
net
274拠点
公式サイト
※Google検索「グループホーム フランチャイズ」の検索上位12社の内、公式サイトにFC展開拠点数を掲載している障がいのある方向けグループホームのフランチャイズ本部を調査。その数が多い上位3社を選定しました(2022年6月9日調査時点)。