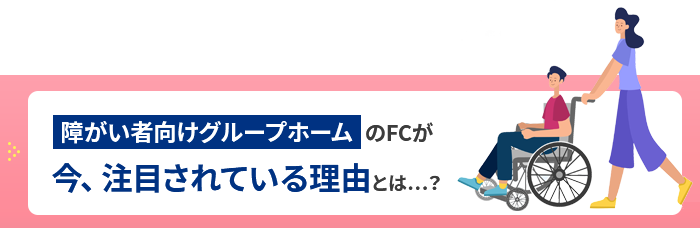障がい者グループホームでのトラブルと対策
障がい者グループホームを運営していると、さまざまなトラブルが発生するもの。トラブルの発生は入居者だけに限りません。スタッフが起こすトラブルも数多くあります。グループホームを開業する前に、起こりうるトラブルや対応方法などを学んで、予防に活かしましょう。
障がい者グループホームで考えられるトラブルとは
障がい者グループホームで起こりうるトラブルを、具体的にまとめました。「利用者のトラブル」と「スタッフのトラブル」に分けて紹介します。
利用者のトラブル
障がい者グループホームにおける利用者トラブルは、特に4つの項目がよく発生しやすいと言われています。
- 利用者外出による行方不明
- 騒音トラブル
- 利用者同士やスタッフへの暴力
- 地域の方や近隣トラブル
利用者の方が誰にも何も言わず、ふらっと出かけてしまって行方不明になるのはグループホームではよくあります。障がい者グループホームでは、独り言が多かったり大声や奇声を上げたりする利用者も多く、トラブルに発展することも。マンションやアパートタイプの障がい者グループホームの場合、足音を不快に感じる騒音トラブルもありがちなケースです。自分の感情をうまくコントロールできず、他の利用者やスタッフを叩いてしまうといった暴力もよくあります。
特に注意したいのが地域の方や近隣とのトラブルです。例えば、利用者が障がい者グループホームの窓からじっと覗いてしまい、不快に感じた近隣住民の方からクレームがくるケースがあります。長時間覗いてしまう利用者もいるため、施設側の注意・配慮が必要です。また、目を離したすきに外に出てしまい、ごみ収集所で出されるゴミを漁ってしまうケースも報告されています。
スタッフのトラブル
障がい者グループホームにおけるスタッフのトラブルは、2つのジャンルに分けられます。
障がい者グループホームでは、状況によって利用者の身体を拘束せざるを得ないケースがあります。しかし、不必要な身体拘束をしたり叩いたりといった「虐待」にあたる行為をスタッフが行い、トラブルがおこることもしばしば。障がい者グループホームの利用者は健常者とは違ってスムーズなコミュニケーションが難しいため、スタッフ側が暴言にまでエスカレートしてしまう場合もあります。これも心理的虐待としてトラブルに挙げられるでしょう。
求められる支援をわざとしなかったりコールを無視したりといった虐待行為も、障がい者グループホームで起こり得るトラブルです。金銭トラブルに関しては、利用者の貴重品や金銭などをスタッフが窃盗するケースも報告されています。
障害者グループホームでトラブルが起こった際の対応方法
もしも障がい者グループホームでトラブルが発生したら、施設としてはどのような対応をするべきなのでしょうか。対策を紹介します。
利用者のトラブルへの対応方法
利用者のトラブルは、4つの方法でスムーズに対応しましょう。
- 利用者とスタッフにコミュニケーションを積極的にとってもらう
- 周辺施設のスタッフにも協力してもらう
- スタッフ全員の対応を統一する
- 家族に普段から利用者の様子を細かく伝える
自分の思いや要望をうまく伝えられないもどかしさが、利用者の暴力や暴言につながっている場合もあります。できるだけ日頃からコミュニケーションを取り、信頼関係を構築しておくのが大切です。行方不明になったり周回したりなどのトラブルは、周辺施設のスタッフとも連携したほうがスムーズに解決できます。
スタッフ全員が同じ対応を取ることで、人による対応の違いが予防可能。また、利用者のご家族と密に連絡を取るのもトラブル回避のポイントです。「問題行動があまりに目立つ場合は、施設利用停止になる」こともしっかり事前に伝えておきましょう。
スタッフのトラブルへの対応方法
スタッフのトラブル防止には、充分な人員確保と現場の声のヒアリングが効果的です。仕事におけるスタッフのストレスや不満は、仕事のクオリティ低下にもつながります。例えば、利用者の虐待防止につながるように個人配置ではなく複数担当にして、できるだけスタッフの負担を減らすのもひとつの方法です。正社員でなくパートや派遣スタッフなどの雇用形態パターンを増やし、働きやすい環境作りも心がけると、トラブル予防につながります。
【ケース別】障害者グループホームのトラブルの対応例
行方不明
食事や入浴の際、さりげなく確認をします。玄関の出入りにはとくに注意し周囲と連携して対処。徘徊リスクがある人はとくに注意が必要です。夜間の施錠も重要で人感センサー付きチャイムの設置も検討しましょう。万が一いなくなったら職員全員で捜索し、家族への連絡や警察に捜索願を出します。
騒音
防止策として、吸音材や防音パネルの設置を検討します。制止しても大声や奇声などが続くなら場所を変えて利用者と距離を起きます。
利用者からの暴力
受け入れ前から暴力の情報があるなら受け入れを拒否します。入所後の暴力は理由を探り、繰り返し注意してください。知的障がいがあるなら他の利用者と距離を置くようにします。介護記録には事実ベースで客観的に記録を残してください。
近隣トラブル
開業前は事前に住民説明会で丁寧な対応してください。施設内で行える予防策は徹底的にします。万が一トラブルがあれば謝罪。同時に今後起きないようどんな対策をするか説明します。も行いましょう。
利用者の問題行動を理解することが大切
グループホームでよくある利用者の問題行動を掘り下げると行動障害に行き当たります。行動障害は利用者の行動特性と環境が条件です。2つの条件がそろうと行動障害が出てトラブルに発展します。
行動障害の予防と対策で頭に入れておきたいのは「利用者もなにかを訴えようとしている」点です。奇声は、不満の発散、要求、自分なりのコミュニケーションの場合があります。そのうえで、利用者本人が望む環境づくりがグループホーム側に求められます。
グループホームのスタッフも行動障がいへの深い理解が必要です。行動援護従業者要請研修で研修できるため、スタッフが参加できる体制を整えましょう。知識を共有した上で、利用者が問題行動を起こさないためにしっかりと予防と対策を徹底してください。
オススメのグループホーム
フランチャイズ3選
Kensei 共生.
net
274拠点
公式サイト
※Google検索「グループホーム フランチャイズ」の検索上位12社の内、公式サイトにFC展開拠点数を掲載している障がいのある方向けグループホームのフランチャイズ本部を調査。その数が多い上位3社を選定しました(2022年6月9日調査時点)。